研修医案内(小児科)
卒業後3年目以上(初期研修終了後)のドクターが対象です。研修期間は原則3年間としています。
研修システムの特徴
りんくう総合医療センター小児科は、2011年度に日本小児科学会専門医研修施設に認定され、3年間の研修が終了後には、小児科専門医の受験資格を取得できます。また、日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度指定研修施設に認定されています。当院小児科では、周産期医療を中心に、一般小児科診療・一次二次小児救急を研修できるため、幅広い年齢層を対象とした小児科診療が可能です。ただし、白血病などの悪性新生物、自閉症・ADHDなどの児童精神心身領域や一部の専門分野は診療対象外としています(これらの疾患については、関連施設を含め希望に合う研修コースを組み上げていくことは相談可能です)。
周産期医療
りんくう総合医療センター産科は産婦人科診療相互援助システム(OGCS)、小児科は新生児診療相互援助システム(NMCS)に参加し、2007年には地域周産期センターに認定され泉州地区周産期医療の活動拠点となっています。OGCSからは緊急母体搬送の受け入れ、NMCSからは疾病新生児や早期産児の搬送を受け入れており、2001年9月以降、NICUへの早期産児受け入れ基準は、在胎25週以上・出生体重500g以上としてより早い時期の母体搬送症例を受け入れています(重症先天性心疾患・小児外科疾患は受け入れていません)。休日・夜間はNICU当直1名、産科当直2名で診療を行っています。NICUでの診療は、シフト制(当番医が診療を主に担当)で朝夕のカンファレンスで決定された方針を元に、当番医が行っています。病状説明等は主治医が担当しています。 NICUは、赤ちゃんとご両親の絆の形成を援助し愛情を育める場所としてのNICUをめざして努力しています。お母さんご自身の母乳で退院後も育てていけるよう、また、生まれたばかりの赤ちゃんと出産を終えられて間のないご両親が、安心して歩みだされるよう支援していきたいと願っています。 産科病棟は2010年春から母児同室となりました。正常妊娠・正期産のお産は帝王切開も含めて年間約1,000件で、母乳育児を支援し親子の早期愛着形成と健全な母子の成長を促すことを願って母児のケアを行っています。正常新生児に対しては、新生児診察、退院時診察、1ヶ月健診を行っています。
一般小児科診療
外来診療は、午前診は2013年4月以降、月~木は2診制、金曜3診制で行い、直接の指導医が担当する外来曜日の2診を担当します。いわゆる一般小児科外来で、病診・病病連携による紹介患者も受けています。午後診は慢性患者の予約外来、1ヶ月健診、月1回の小児循環器専門医による循環器外来、予防接種(早期産児へのシナジス、アレルギー児・その他の重症児へのインフルエンザワクチン、当センター出生児の定期・任意接種)を行っています。
小児科病棟は6床、入院疾患は肺炎・気管支炎・気管支喘息発作・川崎病、等の急性期疾患が中心です。
小児救急
平日日勤帯(17時まで)は、消防隊からの救急診療要請には原則すべて対応しています。泉州二次医療圏(和泉市・泉大津市以南) での夜間休日小児救急医療体制は、土曜・日曜・祝日の日勤・準夜帯では、一次救急はまず泉州北部小児初期救急広域センター(岸和田市)で行い(繁忙期3診制、閑散期2診制)、その当日の深夜帯(23時以降)、および平日夜間は泉州地区7病院(泉大津市立病院、和泉市立病院、岸和田徳州会病院、市立岸和田市民病院、市立貝塚病院、りんくう総合医療センター、阪南市民病院)の輪番体制で小児救急を担当しています。当院からは泉州北部小児初期救急広域センターに2回/6ヶ月出務しています。 輪番当番は、第2、4週日曜日の準夜深夜帯(23時から6時まで)を担当しています。小児救急全般を通じ、三次救急もしくはそれに近いより高度な医療を必要とする場合、りんくう総合医療センターに併設する泉州救命救急センターに収容されます。
泉州保健医療圏の輪番制による小児科救急診療スケジュール
指導体制と研修プログラム
| 指導者 | |||
|---|---|---|---|
| 山本 昌周 | 小児科部長兼新生児医療センター長 | H.11年 愛媛大学卒 | 小児科専門医 |
| 立石 美穂 | 小児科医長 | H.16年 福井大学卒 | 小児科専門医 |
| 三原 聖子 | 小児科医長 | H.19年 大阪大学卒 | 小児科専門医 |
| 浦上 裕行 | H.30年 香川大学卒 | 小児科専門医 | |
| 辻田 麻友子 | H.21年 大阪大学卒 | 小児科専門医 | |
| 田上 利樹 | R.04年 関西医科大学卒 | ||
| 住田 裕 | S.54年 自治医大卒 | 小児科専門医 | |
小児科診療の出発点である周産期医療から、一般小児科、小児救急、すべてをオールラウンドに診療できるような研修を目指し、それぞれの診療は、曜日ごとの勤務表(当院小児科に勤務する医師各人をそれぞれのパートにほぼ均等に割り当て)に従って行っています。研修3年目は、阪大(または府立母子保健総合医療センター)でより高度な小児医療を研修する予定となっています。
周産期医療
NICUでの診療方針は毎朝夕の回診で決定し、日々の実際の診療はNICU当番医および当直医が行っています。超低出生体重児から疾病成熟新生児まで多種多様な疾患・病態を経験でき、気管内挿管、末梢・中心静脈ライン確保、動脈ライン確保、ベッドサイドでの超音波検査は必須習得技術です。初期は指導医もしくは常勤医がフォローしますが、おおよそ3~6ヶ月後には一人で行える程度に習熟できると考えています。呼吸補助の技術として、正期産分娩でも、在胎37週台での帝王切開など、子宮外への適応障害(肺胞液吸収遅延など)に対して、face mask CPAPを行うこともありますし、face mask baggingも含めて是非周産期医療でマスターしてほしいスキルの一つです。
NICUでは御家族は様々な不安と孤独に戦っておられます。集中治療のなかで母児と御家族を中心にそえた医療(Family centered care)ができるようにスタッフと(時にご家族を含めて)相談して考えていくことも必要です。当院での研修を通してこのような過程を経験し習得していきます。
産科病棟では、出産後のカンガルーケアやスタッフ一同で系統立てて母乳育児を支援することで母と子の愛着形成をサポートできるよう勤めていきます。また、新生児の診察、母親とのコミュニケーションを通して育児上の不安や心配事を傾聴することも大切です。
一般小児科診療
外来診療:直接の指導医が担当する外来曜日の2診を担当します。担当医として、問診・診察・検査スケジュールをたて、鑑別診断を踏まえて検討し、診断・治療を行っていきます。必要であれば他科に紹介し、相談して診療にあたります。また、周産期センターや小児科病棟からの退院児のフォローのため、1日/週、午後の予約外来(慢性外来)を担当します。小児科病棟に入院となった患児には、主治医として対応します。毎週1回、1ヶ月健診(月曜日あるいは木曜日)を担当します。
救急医療:平日の救急隊からの救急搬送診療要請への対応、また時間外の病診連携診療を救急外来で行います。入院の必要な患児はその日の小児科病棟担当医と連携して、入院診療を行います。輪番担当日(第2・第4日曜日)には、一次救急患者の中に、見落としてはならない救急疾患(腸重積症など)を見抜く力をつけていきます。救急外来での短い診療時間内での保護者とのコミュニケーション能力は、毎週の一般外来を丁寧に且つ迅速に行うよう心がけ、「何故来院されたのか」をご家族の立場で考えて理解する癖を身につけることで培っていけると考えています。
小児保健:少子化の現代、健全な親子関係を築き、いろいろな育児上の心配事に小児科医がアドバイスすることがより重要になってきています。小児科医として育児指導を上手く進めていく技術を身につけていただくことが求められており、後期研修2年目以降、近隣の保健センターに出向いて、一般乳幼児健診(4ヶ月児健診等)、二次健診を月1回程度担当します。
勤務体制
| 小児科 (りんくう総合医療センター) 週間スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:30~9:00 | NICU回診 | NICU回診 | NICU回診 | NICU回診 | NICU回診 |
| 17:00~ | 病棟回診 GCU回診 NICU回診 |
NICU回診 | NICU回診 | NICU回診 | NICU回診 |
| 17:30~ | 産科との合同 周産期カンファランス 小児科医局会・抄読会 |
||||
年間スケジュール
■春・秋…泉州小児科勉強会
■1~2回/2ヶ月;NMCS例会
■日本小児科学会
■日本周産期・新生児学会
■日本未熟児新生児学会
■その他
研修終了後の進路
小児科専門医試験を受験し、合格後、当院小児科常勤医として勤務を継続することも可能です。小児科のサブスペシャリティー(新生児専門医、小児循環器専門医、など)を目指す場合、該当する医療機関でさらなる研修を積むことも可能です。当院で可能なのは新生児専門医で、小児科専門医取得後の3年間に大阪府立母子保健総合医療センターなどの総合周産期センターで半年以上の研修を積めば、新生児専門医の受験資格が得られます。その他、希望する医療機関があれば希望に添うよう相談できます。
お問合せ
給与や待遇など詳細については、下記までお問合せください。
りんくう総合医療センター 総務課
〒598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23
TEL:072-469-3111(代)


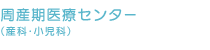 りんくう総合医療センター
りんくう総合医療センター
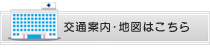
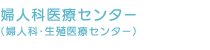 市立貝塚病院
市立貝塚病院



